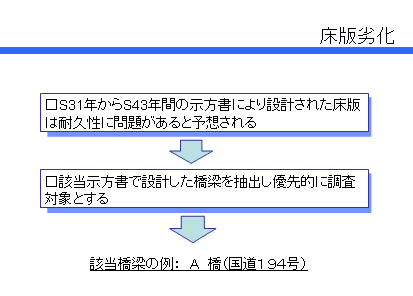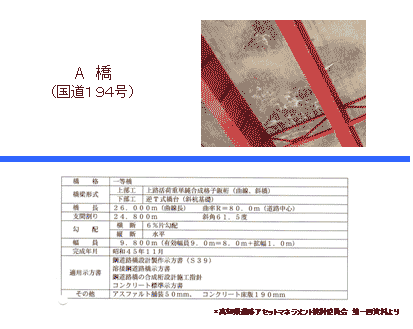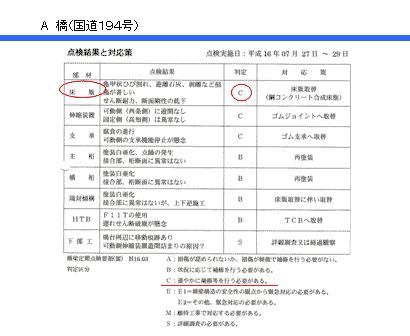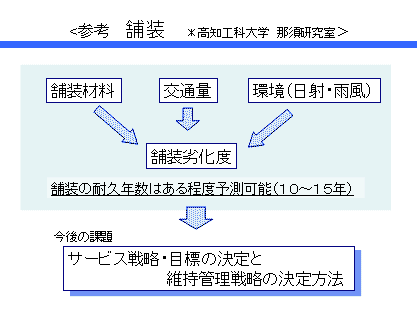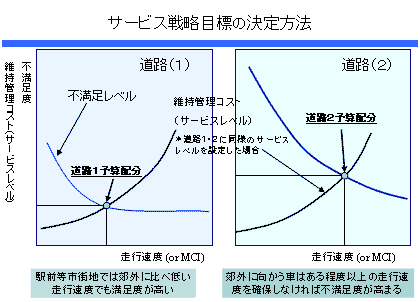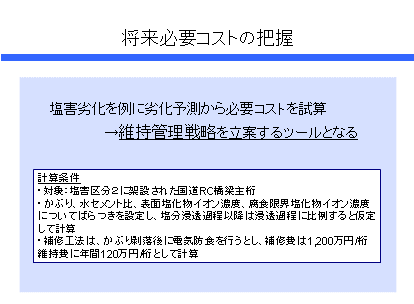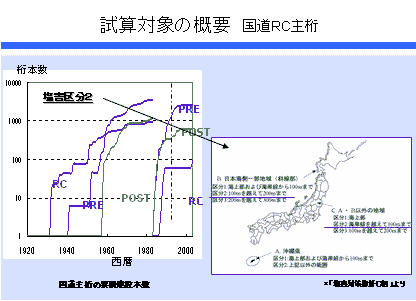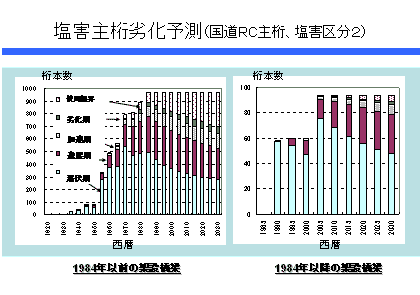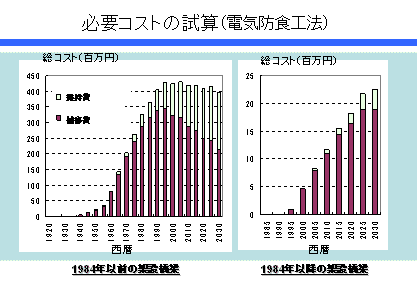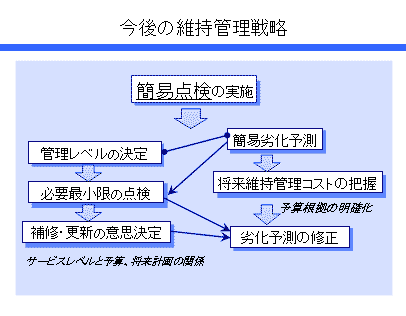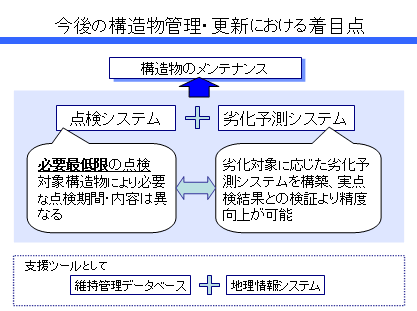 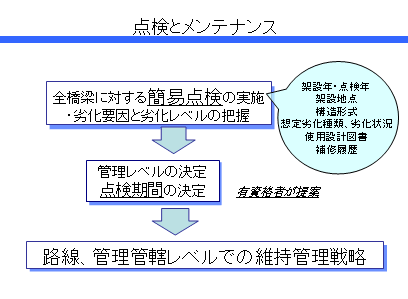 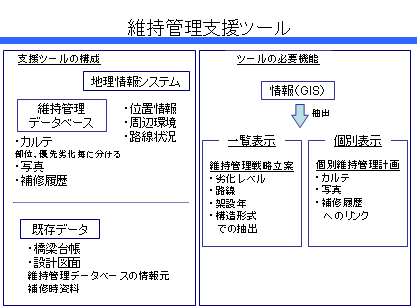 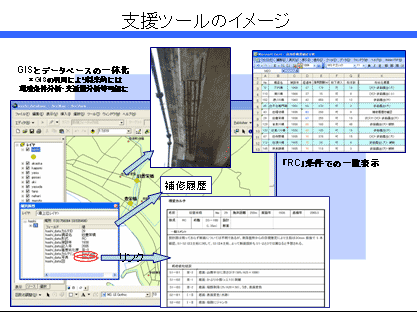 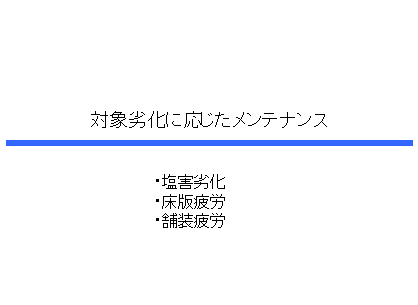 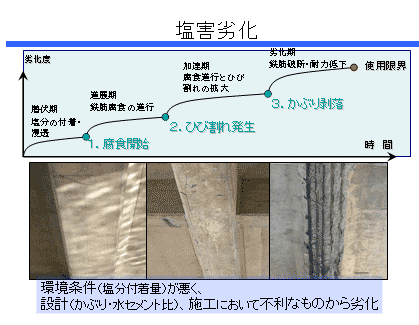 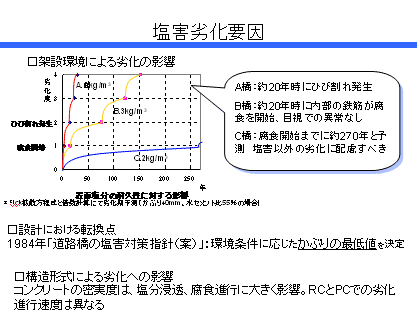 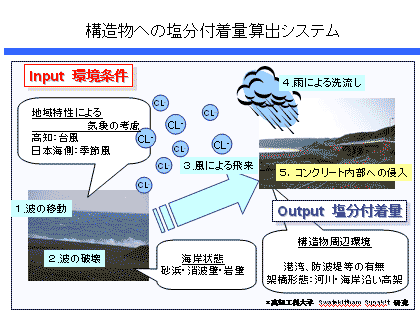 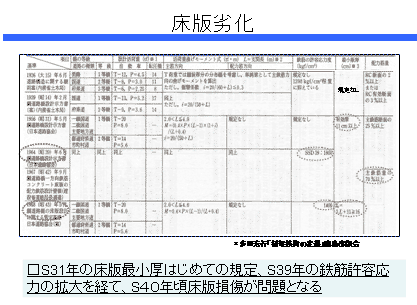 |
構造物の維持管理を、点検システムと劣化の予測システムとを組み合わせて行うことが良いと数年前から提案しています。そして、劣化予測に役に立つ最小限の点検を行うのが良いというのが私達の主張です。
過度または過少に点検をするのではなく、劣化予測システムとメンテナンスに役立つ点検をすることが大切です。点検をし、将来予測と合わせて、危ないと判断されればすぐに手を打たなければいけないし、当分危なくないと判断できれば、点検も大幅に省くことができます。その仕分けをするためには、点検と劣化予測のシステムとの連携が必要です。なお、このシステムを支援するツールとして、管理データベースと地理情報システムが役立ちます。 データベースに入っている、架設年、架設地点、構造形式、使用設計図書、補修履歴に、簡易な点検による劣化状況の把握を加えます。これと劣化予測システムとを合わせて、管理レベルや点検期間の決定を、これらに精通した資格者が行うことを提案しています。 維持管理支援ツールの、地理情報システムと維持管理データベースについて述べます。 この地理情報には、構造物の位置やその周辺情報、路線の状況等が含まれています。維持管理データベースには構造物のカルテ、点検時の写真、補修履歴等が含まれています。既存のデータとして、橋梁台帳や設計図面がありますので、これらの必要事項を取り入れておきます。 支援ツールのイメージの一例です。 地理情報システムの地図上の橋梁をクリックするとそのデータが現れます。なお、このシステムに環境条件や交通量をも含ませるのがよいと思います。 対象劣化に対応したメンテナンスについて、鉄筋コンクリートの塩害と床版劣化および舗装をとりあげます。 塩害劣化の進み方、すなわち、内部の鉄筋の腐食がはじまり、ひび割れが発生し、コンクリートかぶりが脱落し、最終的には供用限界を超えるというプロセスを示したものです。 コンクリート内部にある鉄筋の腐食開始時点は、塩分がコンクリート表面に付着して内部に浸透していき、鉄筋位置まで到達して、その位置の塩分濃度が腐食を開始させるに足る量となる時点を意味します。その時点ではもちろん外観上は何の変状も認められません。鉄筋腐食の進行によって鉄筋が膨張し、その膨張力によってコンクリートには引張力が発生します。この引張力による応力がコンクリートの引張強度を超えるとひび割れが発生します。このひび割れは通常鉄筋に沿って現れます。このひび割れが発達し、次の段階は鉄筋の外側にあるコンクリートが剥がれ落ちる状態です。 この写真は、その状態を示しています。なお、鉄筋は破断していません。ひび割れ発生以後の状況は橋梁の外観から判断できます。 塩害は環境条件によって大きく異なります。図のAは塩害が厳しい環境、Bは中くらいの環境、Cはほとんど塩害を受けない環境を意味しています。横軸は建設後の経過年数です。腐食開始、ひび割れ発生、かぶり剥落、供用限界、この4つの段階のどの段階にいつ頃なるかという予測を示したものです。この例はかぶり40mmで水セメント比55%のものです。例えば、環境条件Aでは建設後20年でひび割れが発生することを意味しています。環境条件Bである地点に造られた鉄筋コンクリート桁は建設後20年で鉄筋の腐食が開始し、目に見えるひび割れが70年後に発生することになります。ところが環境条件が極めて良いCでは腐食開始が200年後です。ラフな予測モデルですが、今後改良して精度を上げていく予定です。 現存の鉄筋コンクリート構造物の塩害に対する抵抗性は、建設した時期によって明らかに異なります。西暦1984年に道路橋の塩害対策指針が公になり、それ以降の構造物はそれ以前のものと比べて塩害に対する抵抗性が著しく改善されているからです。耐震性についても設計法が大きく変わった年の前後で全く耐震性能が異なりますが、塩害の場合は1984年がキーの年であるといえます。塩害は、表面から塩分が中に入ってくるのが現在では主たる理由ですが、一時期に打設時に既に塩分が入っている場合がありました。海砂をあまり洗わないで使っていた時期です。フレッシュコンクリート中の塩分を厳しく規制しはじめた年も一つのキーの年になります。 一つの構造物の劣化を予測することについては、多くの研究がなされて、かなりのことが解っています。今一番不明確なのは、その構造物に、どの位の量の塩化物がいつ飛来して来て、その表面にどれだけの塩化物が付着しているかということです。風が吹けば塩化物が飛来して来ますが、雨が降れば飛来する量が減るだけではなく、それまでコンクリート表面に付着していた塩化物がある程度流されてしまいます。これらのことが分かれば、塩害による劣化予測は相当な精度で行うことができます。今その研究を進めています。それは丁度、ある時点にどのような地震波が来るかということがわかれば、その構造物が安全であるかどうかが予測できるのと同じことです。ある地点にどのような地震波が到達するかについては、かなり研究が進んでいて、ある程度の精度で予測できます。それは地震学者がこの2~30年間総力を挙げて研究してきた結果です。津波も同じですね。しかし、塩害については、その研究が今までほとんどやられていませんでした。現在、私たちはこの問題に取り組んでいます。 飛来塩分の源は、海です。波がしぶきをあげて、空中に塩化物を放出し、風に乗って飛んできて、構造物に付着します。場合によっては雨によって洗い流されもします。表面に付着した塩分はコンクリート中に浸透していきます。塩分のコンクリート中の移動についての研究は、随分進歩しており、精度の良い予測ができる状況にあります。入力地震波が与えられると構造物がどのように反応するのかを精度よく予測できるのと同じです。 今までに判ったいくつかのことを話しましょう。高知であれば台風の時に飛来する塩分が圧倒的に大きな影響があります。それ以外の時の塩分飛来量はたいしたことではありません。そして、波が高いときに南風が吹いた時が重大です。北風が吹いても構造物に向かって塩化物は飛んできません。 |