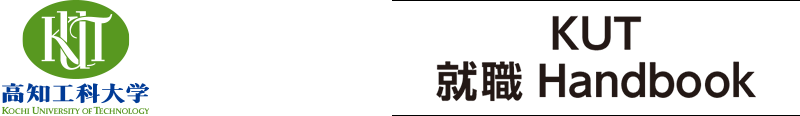Lesson22
OB・OG訪問
社風を知るには、先輩社員の話を聞くのが一番。自分でもルートを探して訪問しましょう。
OB・OG訪問は必ず行わなければならないというものではありませんが、より深く企業研究を行ったり、具体的な仕事内容を知ったり、企業の雰囲気を知るには、そこで実際に働いている人に直接会ってみて、生の声を聞いてみるのが一番です。自分で積極的にルートを探してみましょう。
1アポイントの取り方
(1)OB・OGを探す
●卒業生・研究室・サークル等の先輩から探す。
●就職支援課に相談する。
●企業に直接問い合わせる。
志望する企業にOB・OGが見つけられない場合は、人事部に連絡をして紹介してもらうことも可能です。
*「個人情報保護法」によりOB・OG訪問の依頼が断られる場合があることを念頭に置いて訪問先を探すようにしましょう。
(2)電話やEメールでアポイントをとる
直接OB・OGに電話をしてアポイントをとる場合と、Eメールなどで連絡をとってお願いする場合があります。最初にEメールでお願いした場合でも、後で直接電話して具体的な日時を確認しましょう。
ただし、お会いする方が信頼できる相手であることを必ず確認し、非常識な時間や場所で会うことのないように注意します。
(3)OB・OGに会って話を聞く
アポイントが取れたら、実際にOB・OGに会って話を聞きましょう。話を聞く前に、自分が聞きたいことを簡潔にまとめることをお勧めします。疑問に思うことは進んで積極的に質問しましょう。目指している企業の話を生で聞くことができるOB・OG訪問はたくさん行っておいて損はありません。その業界や企業に対して詳しくなり、またOB・OGの話を聞くことで就職活動を多角的な観点から進めていくことができるようになります。OB・OG訪問をする際に忘れてはならないことは、あなたが「教えてもらう」立場だということです。決して先方に失礼のないように気を付けましょう。
(4)訪問後のフォローを考えておく
OB・OGはわざわざ時間を割いてくれています。必ず感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。
訪問のお礼を手紙で送る場合の注意点
お礼状の書き方「Lesson26」のように、手紙の書き方のルールに沿った文面にしましょう。文面形式は、頭語から始まり前文、本文、末文、結語で終わります。前文に自分は誰かを述べ、主文にその人を知った経緯や、その会社のどんなポイントに興味を持ったのかなどを書くのも良いでしょう。
2訪問時の心構え
(1)訪問準備
- ●志望動機と自己PRをまとめておく……「予備面接」の意味もあるので簡潔・明快に話せるようにしておく。
- ●基本情報はインプットしておく……会社案内で分かる情報をわざわざ質問しないようにしておく。
- ●質問事項はまとめてメモしておく……先輩に貴重な時間を割いていただくので時間を無駄にしないようにする。
(2)訪問時の注意点
- ●遅刻厳禁……遅くとも約束の10分前に待ち合わせ場所に着くようにする。
- ●長くても30分~45分……むやみに長話にならないようにする。
- ●言葉遣いは丁寧に……「先輩だから」と甘えてなれなれしい態度は禁物。
- ●相手の話をよく聞く……明るくハキハキと的確な受け答えをする。
(3)質問のポイント
OB・OG訪問の目的は、情報収集、志望意思の伝達、本選考前の予備練習です。それを踏まえたうえで、企業研究での疑問点を質問しましょう。そうすればあなたが就職活動にどう取り組んでいるのか、どんな企業研究をしたのかをOB・OGに伝えることができます。また、OB・OGは就職活動の先輩でもあるので、先輩の体験談やアドバイスも貴重な情報となります。いくつか質問例を挙げておきますが、あくまでも参考ですので、自分でしっかり質問事項をまとめておきましょう。
①職場の雰囲気
- ・上司と部下の関係
- ・同僚との人間関係
②仕事内容
- ・具体的にどんな仕事をしているのか
- ・ほかの社員はどんな仕事をしているのか
③就職活動について
- ・説明会や会社訪問などOB・OGが体験したスケジュール
- ・一番苦労したこと
- ・成功のポイント
- ・やっておいて役に立ったこと
④試験内容について
- ・書類選考の有無
- ・面接の回数とやり方
- ・よく聞かれる質問、印象に残った質問
- ・筆記試験の重要度と出題傾向
- ・注意すべき点
Check Point
Check Point 1
アポイントを取る際の注意点
OB・OGの連絡先が分からない場合、企業の代表電話にかけて事情を説明するのも一つの方法です。大企業では電話の相手が複数に及ぶこともありますが、そのつど、学校名と氏名を名乗る必要があります。
Check Point 2
質問は具体的に
卒業生に対して、知ったかぶりや決め付けで話をしないようにしましょう。また、漠然とした質問ではなく、より具体的な質問ができるように用意しておきましょう。