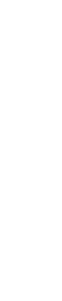VOL. 04 / 04
高知で「世界一流の大学」、
「日本にない大学」をつくる
世界にないものを創り出した研究者の姿勢は、教育においても変わらなかった。東京工業大学の学長を務めていた1993年、橋本 大二郎 高知県知事(当時)から要請を受け、高知工科大学の創立に際し、その具体像を策定する「工科大学計画策定委員会」の会長に就任した。
末松先生は、「せっかく新しい大学をつくるのなら、世の中が本当に必要としているものでなければいけない」と考えた。目指したのは「人間力教育の実践の場となる大学」だ。
人間力とは、「自制心や協調性、倫理観など社会的に行動する力」「自己啓発力や好奇心といった自ら知識を広げたり深めたりする力」「創造性や判断力などの考える力」、そして「意思疎通のための対話能力」のことを指す。この人間力の概念には、末松先生のこれまでの歩みがよくあらわれている。
末松先生はこうした人間力の育成こそが、社会が大学に求めていることであり、また学生にとっても、今後の混沌とした社会を生き抜くために欠かせないことだと確信。策定委員会の会長として大学の具体像を固めていくなか、初代学長への就任をたびたび要請された。
「最初はあまり乗り気ではなかったのですが、話を聞くうちに『高知でなら、教育の最先端を開拓する大学が実現できるかもしれない』と思うようになりました」
実際、末松先生は開学後のインタビューで、「高知の人は自分の意見を通すようなところもあるが、一方で世の中のためにやってやろうという気概もある。坂本龍馬に代表されるような底知れない『でかさ』がある別格の土地。そういう風土だから、短期間にこれほどの大学がつくれたのだと思う」と語っている。設立に際し、県をあげて優秀な人材の職員が送り込まれた。そして、高知から新しい大学の理念が発信され、日本全国から志の高い教員が集まった。
末松先生自身もアイデアを次々と実行に移し、これまでにない学びの場を創りあげていった。たとえばキャンパスづくりにも積極的にかかわり、当初の計画案では学科ごとに分かれていた建物を、ひとつの棟に集約。また、教員室の面積を削ってまで廊下を広くとって、教員と学生が気軽にコミュニケーションをとれるコモンスペースを設けた。
「議論は廊下でやろう、ということです(笑)」

美しい前庭をはじめ、広々とした緑が映えるキャンパスの配置も、末松先生の発案だ。

このようにして、高知工科大学が現在も目標に掲げる「世界一流の大学」の基礎が築かれていった。末松先生は4年間、学長を務め、2001年に岡村 甫 第2代学長にバトンをつないだ。
初代学長を退任した翌年、末松先生の自宅にもNTTの光ファイバ回線が開通した。「工学は、社会のシステムで活きてこそ意味がある」と考える末松先生には、感慨深いものがあっただろう。2004年には、末松先生が「本命」に据えていた波長可変DBRレーザがアメリカでようやく実用化され、1年後には日本でも活用されるようになった。光通信の研究をはじめた1960年代初頭に、「いま研究をしても、実用化までに少なくとも四半世紀はかかる」といわれたそうだが、実際には40年かかった。それでも、頭に描いていた未来はやってきた。「研究は未来を引き寄せる」が末松先生の口癖だ。それは、いまを生きる学生にも当てはまる。
「Googleの共同創業者であるセルゲイ・ブリンにラリー・ペイジ、Facebookのマーク・ザッカーバーグなどを見てもわかる通り、学生であっても大きなチャンスをつかめる時代が到来しました。あとは意識だけです。世界の最先端を覗き、そして覗くだけではなく、自分でやろうと思うことが大切です」
世界を美しい光でつないだ末松先生の功績は、2014年に日本国際賞、2015年には文化勲章が授与されるなど、情報化社会の成熟が進むとともに、改めてその価値が評価されている。

故郷の中津川市では、科学の魅力を伝える夏休み教室を毎年開催し、20年以上講師を務めている。そこには、手製の望遠鏡で星空を覗いたあの頃の自分と同じように、科学にふれて目を輝かせる地元の中学生の姿があった。次代を担う若者たちが、どんな未来を引き寄せるのか──。末松先生は、大きな期待を込めて見守っている。

- 04
- 04