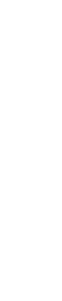VOL. 03 / 04
世界一を目指した研究が、
人々の心を惹きつけた
末松先生は研究を進めるうちに、光ファイバを使った通信の光源として、半導体レーザを使うことを見出した。大容量かつ長距離の光通信を実現するためには、光源として光ファイバが最低損失となる波長帯で安定した機能を発揮するレーザの開発が急務。企業の研究所などレーザ開発の担い手を探したが、手を挙げるところはなく、末松先生の研究室で独自に挑戦することになった。「大学で半導体レーザをつくるのは無謀」という指摘もあったが、末松先生はそんな声に屈すことはなかった。実際、1974年には分布反射器を2つ使った画期的なレーザの構造を提案するなど、理想とする光通信へと向かう道筋はつけていたのだ。
しかし、いざレーザの開発に取り組んでみると、苦難の連続だった。たとえば、光ファイバの損失を最低に抑えた波長帯で働くレーザの開発では、インジウム・リン基板とガリウム・アンチモン基板という2つの選択肢から、より適した基板を選ぶ必要があった。当然、どちらが正解かという確証はない。一方を選択して研究を進めると、5年は後戻りできなくなる重い判断だった。末松先生は溶解温度が高く硬さもあるインジウム・リン基板を選択した。
「ずいぶん悩みましたが、こういう場面では、もう自分の直感を信じるしかないんです」
インジウム・リン基板は当時イギリスにしかなく、「金(ゴールド)より高価」というほど貴重なものだった。調達には費用的な壁が立ち塞がったが、当時KDD研究所の所長を務めていた中込 雪男 氏が、「私が全部サポートするから、心配なくやりなさい」と支援を申し出てくれたという。
「私が光通信の研究をはじめた当初も、山崎 貞一 TDK社長が、『世界一の研究をやるなら、いくらでも支援する』と多額の寄付をしてくださりました。金額もさることながら、『これで本当の研究がやれるぞ』と勇気をいただきました」
末松先生の研究人生には、企業人や研究者など、要所要所で支援をしてくれる恩人があらわれた。研究をともにした教え子も含め、「私は本当に、人に恵まれていた」と末松先生はしみじみ振り返る。

このようにして長年積み上げていった研究成果を組み合わせ、1980年、ついに通信用半導体レーザ(動的単一モードレーザ)が誕生した。
大容量長距離光ファイバ通信への道が、明確に開けた瞬間だった。その翌年、研究室から巣立った2人の教え子が、それぞれNTTとKDDに就職し、両社での実用化にも成功した。「じつに愉快な産学連携でした」と末松先生。
さらに第2世代の「位相シフトDFBレーザ」や最終形態となった「波長可変DBRレーザ」など、機能を拡充したレーザも相次いで開発し、現在に至る情報通信の根幹を担う技術が完成した。末松先生は、位相シフトDFBレーザが通信用レーザとして商用化されるのを見届けて、研究の一線から身を引いた。そして1989年、東京工業大学の学長に就任し、教育者として新たなスタートを切った。