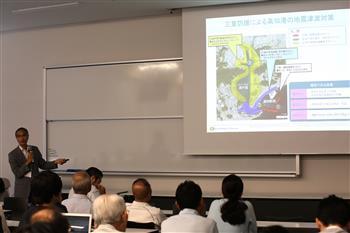- トップページ
- NEWS & TOPICS
- 昭和南海地震70周年シンポジウムに学長が登壇しました
2016.9.28お知らせ
昭和南海地震70周年シンポジウムに学長が登壇しました
9月27日、永国寺キャンパスにおいて「昭和南海地震70周年シンポジウム -来たるべき南海トラフ地震への備えを考える-」(日本地震工学会、日本地震学会共催)が開催され、磯部 雅彦 学長が講演し、パネルディスカッションに登壇しました。
会場には、学会の研究者、学生、自治体防災担当者、地域の方々など170名が参加し、熱心に聴講されていました。
はじめに、地震と津波のメカニズムにおける著名な研究者、日本地震学会副会長の古村孝志 東京大学教授が「見えてきた、南海トラフ巨大地震の姿」と題し、近年の内陸型地震の活性化と、来るべく南海トラフ地震との関連性、今できる事前の地震津波対策の重要性などについて講演されました。
続いて、地震工学における著名な研究者 地震工学会会長、目黒公郎 東京大学教授が「最近の地震災害から学ぶ教訓と今後の我が国の防災対策のあり方」と題し、東日本大震災の津波で破壊された各地の堤防が、津波到達遅延や浸水深低減をなし得た事などの説明や、ハード整備と早期避難、住宅の耐震化の重要性などについて力説されました。
続いて、本学の磯部雅彦学長により「津波防災対策のあり方と高知県の取り組み」と題し、東日本大震災のデータから科学的に解析された津波発生のメカニズム、次の南海トラフ地震の、県内各地での津波到達の想定等を解説した後、高知県沿岸各地に90基(建設中及び計画を含めると115基)整備された津波避難タワー、高知市で対策が進む、浦戸湾から高知市街地に繋がる高知港の三重防護計画等、先進的な高知県での津波防災対策について講演しました。
パネルディスカッション「来たるべき南海トラフの地震に向けた課題」では、講演者の他、岡村眞 高知大学名誉教授、堀田幸雄 県危機管部副部長が加わり、災害の事前対策、直後対応、復旧・復興のあり方について活発に議論されました。
磯部学長からは、最大クラスの津波は防潮堤を越えてしまうので、事前対策は、地震直後に逃げると決めておく事、直後対応は「津波てんでんこ」を肝に銘じ、一人で知っている道を歩いて逃げる事、復旧・復興は、短期的には自助、共助がうまく出来るかが最も重要で、公助は道路をまず整備し、ライフラインを復旧することが重要であると訴えました。
また、長期的には、元の生活に戻す事より、被災を課題解決の機会と考え、次はどこに住むか等、別の生活を考えることが重要であるなどの提言をしました。
今回のシンポジウムには、70人もの地域の方々が参加し、地震津波工学の研究者と行政が、地域の方々と向き合い議論し情報交換する貴重な機会となりました。
RELATED POST
関連記事