- トップページ
- NEWS & TOPICS
- ―なんのために生まれて 何をしながら生きるがか― <第2回>高高高知講演会を開催
「高知の高校生に最高の知を」――。そんな想いから地域イノベーション共創機構が主催する「高高高知講演会」。4月の開催に続き、第2回目が7月19日に開かれました。
今回の講師は現在、国際研究ネットワークFuture Earthで、さまざまな国籍や専門分野をもつ研究者や実務者たちをとりまとめ、地球や社会の持続可能性に向けた研究を推進する春日 文子さん(長崎大学 教授/Future Earth国際事務局日本ハブ事務局長)。
テーマは「なんのために生まれて なにをしながら生きるがか~ひとりの科学者の想い~」です。
幼いころから動物図鑑が好きで、小学1年の時にはすでに「科学者」になりたい夢を抱いていたという春日さん。望み通り、大学院では獣医生理学を学び、基礎的な研究を重ねて博士号をとりますが、その後、研究室の教授の勧めで選んだ厚生省(現・厚生労働省)の研究所で、思いもよらぬ転機が次々と訪れたといいます。


最初に配属されたのは食品衛生の現場。行政のニーズにあわせ、さまざまな研究を行っていましたが、1996年、あるショッキングな出来事が起こります。
全国で発生した腸管出血性大腸菌O157による集団食中毒です。なかには学校給食で発生し児童が亡くなった事例などもありました。
春日さんは、食品微生物学の研究者という立場で食中毒の原因追究と再発防止に取り組むなか、「自分は子どもの健康を守るために研究をするんだ」という強い使命感をはっきりと感じた大きな出来事であったと振り返ります。
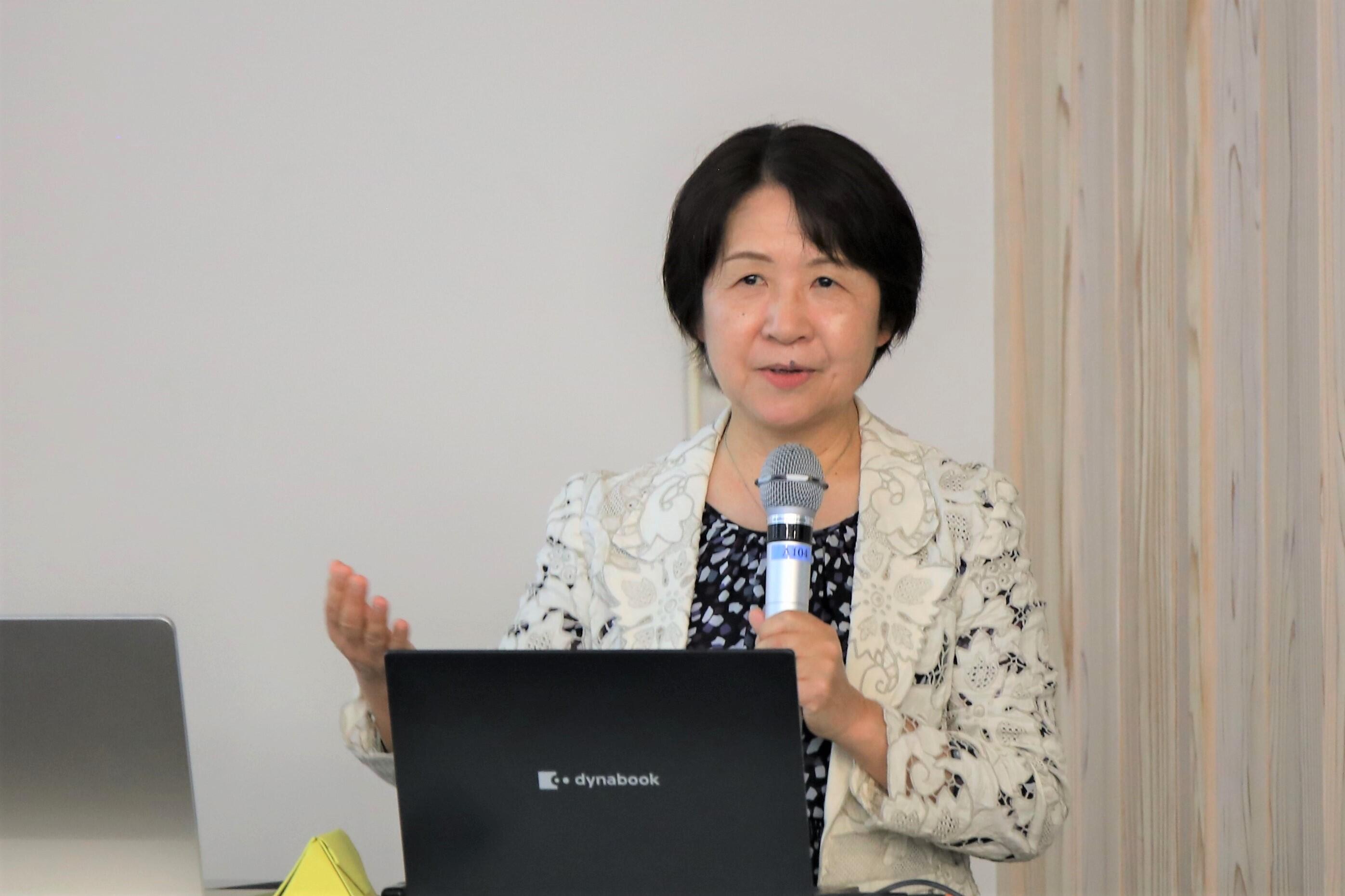
さらに2001年、日本で初めて確認されたBSE(牛海綿状脳症:いわゆる"狂牛病")。
この問題をきっかけに、食品の「リスク評価」を行う部署が内閣府に発足し、春日さんも、数学や物理学、水産学、医学、工学など、これまで接点のなかった研究者とともにチームの一員となります。そこでは、原料の生産から運搬、加工、調理に至るまで、一連のプロセスの汚染確率をモデル化するという、これまでにないシステムをつくりあげ、世界的にも高い評価を得ましたが、リスクを回避するために、もうひとつ大切だったのは「リスクコミュニケーション」だったといいます。
「市民に対して情報を一方的に伝えるのではなく、相手の意見、立場、気持ちを聞くということがいかに大事なのか。相手が何に困っていて、何を知りたいのかということを十分に理解できなければ、役に立つ情報は提供できないんです」。


さらにその頃、日本の代表として食中毒に関わる国際会議に参加する機会も得ますが、英語が飛び交い、めくるめく速さで進む議論についていけず、「自分がここにいていいのか」と発言できない自分に心底落ち込んだそうです。
しかし、そこでめげずに、まずは「午前に1回、午後に1回、何でもいいから発言する」と小さな目標を立て、会議の流れを読みながら挙手をし、地道に取り続けたデータをもとに一生懸命、言葉を重ねます。
すると、日本の衛生環境や、それを支える科学に対し、世界が一目置いてくれていると実感できることが増え、さらには、各地に腹を割って付き合える大切な友人たちもつくることができたといいます。
春日さんが、自身の研究者人生を振り返りながら最も伝えたかったのは、「科学には色々な形があり、基礎研究だけではなく、社会の課題を解決するための科学があること」。そして「課題解決の手法としては、技術革新といった方法のみならず、社会のシステムを改良することで解決しようという科学もあること」だと語ります。


講演会後には、春日さんを囲み、八田 章光副学長がファシリテーターとなって交流会も開催。進路の悩みから、海外での生活、環境に負荷の少ない暮らし方など、通常の講演会ではなかなか聞けないような内容を、和やかな雰囲気のもとで語り合うことができました。
最後に今回のテーマについて改めて問われた春日さん。
「『なんのために生まれたか』は、死ぬまでわからないかもしれませんが、『何をしながら生きるがか』という問いは、毎日毎日考えて、その積み重ねだと思っています」と語り、まさにその言葉どおりの科学者としての生き方を感じることができました。
今年度はあと1回開催が予定されている「高高高知講演会」。詳細が決まり次第、本学HPなどでお知らせします。
【過去の「高高高知講演会」】
2025.5.15 ―高知の高校生へ最高の知を― 高高高知講演会を開催
RELATED POST
関連記事
